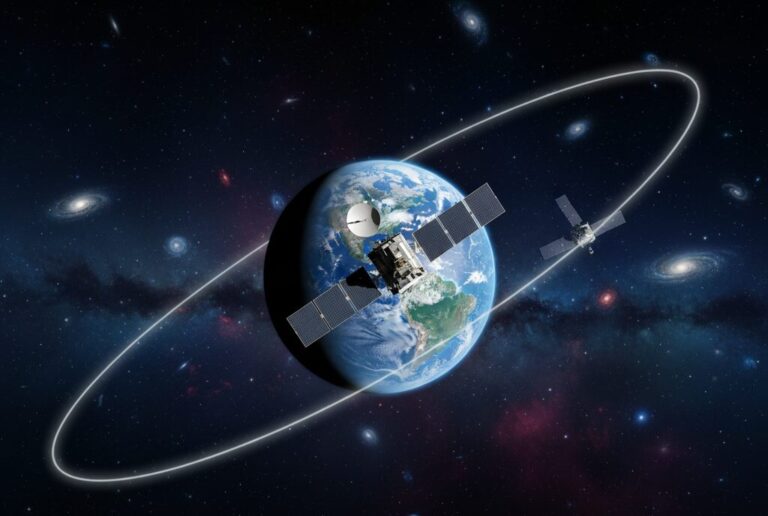遠地点(Apogee)
遠地点とは、月や人工衛星などが、地球の周りをまわる軌道(公転軌道)上で、地球から最も遠ざかった点のことを指します。
地球の周りをまわる天体や人工衛星の軌道は、きれいな真円(まんまる)ではなく、少しつぶれた「楕円(だえん)軌道」を描いています。このため、地球と衛星の距離は、軌道上を移動するにつれて近くなったり遠くなったりを繰り返します。
この楕円軌道の中で、地球の中心からの距離が最大になるポイントが「遠地点」です。
ちなみに、遠地点を通過する際、衛星の飛ぶ速度は軌道上で最も遅くなります。
反対に、地球に最も近づく点のことは「近地点(Perigee)」と呼び、そこでは速度が最も速くなります。
【もっと詳しく】
遠地点は、天体の軌道を示す軌道要素(きどうようそ)の一つである「遠地点距離(Apogee distance)」を定義する点です。
天体が地球の重力によって周回運動をするとき、その軌道は地球を一つの焦点(しょうてん)とする楕円を描きます(ケプラーの第1法則)。この軌道において、地球の中心(正確には地球と周回天体の共通重心)から最も遠い位置が遠地点です。
遠地点距離(地球中心から遠地点までの距離)は、軌道の形と大きさを表す「軌道長半径(きどうちょうはんけい)」を a、軌道のつぶれ具合を示す「離心率(りしんりつ)」を e とすると、以下の式で表されます。
\text{遠地点距離} = a(1 + e)また、ケプラーの第2法則(面積速度一定の法則)により、天体は地球から遠ざかるほどその公転速度が遅くなります。そのため、遠地点において軌道上の速度は最小となります。
この「遠地点」や「近地点」という用語は、中心にある天体が「地球(Geo)」の場合に使われる専門用語です(ギリシャ語の Apo=遠い、Geo=地球 が語源)。
中心天体が地球以外の場合は、より一般的に「遠点(えんてん)」(Apoapsis)と呼ばれます。例えば、太陽が中心なら「遠日点(えんじつてん、Aphelion)」、月が中心なら「遠月点(えんげつてん、Apocynthion)」といったように、中心天体に応じて呼び名が変わります。
【関連キーワード】
- 近地点 (Perigee)
- 楕円軌道 (Elliptical orbit)
- 人工衛星 (Artificial satellite)
- 軌道要素 (Orbital elements)
- 離心率 (Eccentricity)
- ケプラーの法則 (Kepler’s laws)
- 遠点 (Apoapsis)
- 遠日点 (Aphelion)